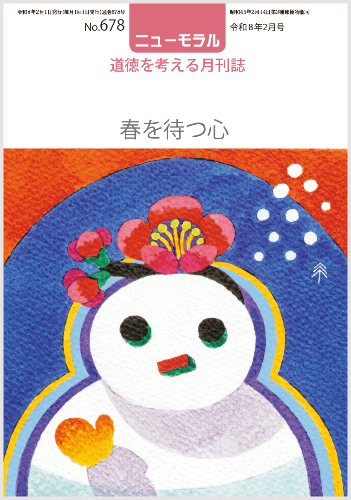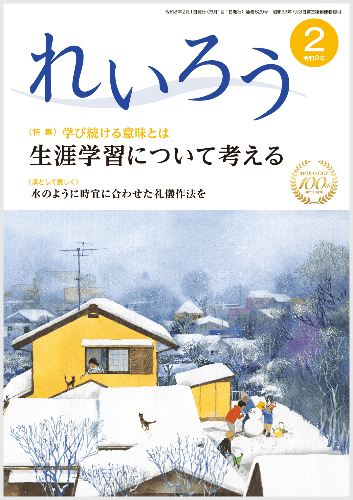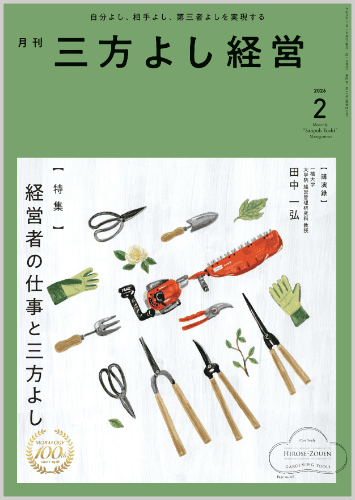人を信用できない人の特徴とは?克服する方法も解説
公開日:2025年03月27日
更新日:2025年06月10日
家族や親しい友達、長く付き合った恋人には心を許せますよね。そのような人間関係や居場所を持っていると、職場や学校で嫌なことがあっても「少しくらいのことならやり過ごせる」ように思えるもの。ですが、世の中にはどうしても「他人を信用できない」タイプの人がいます。人を信用できない人の特徴や人間関係への影響、できるだけ肩の力を抜いて生きる方法についてもご紹介します。
目次▽▲▽
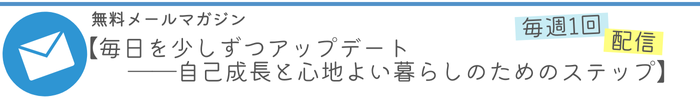


自分も他人も信頼できない人
まずは専門家の視点から、他人を信頼できない人物の特徴を見てみましょう。臨床心理士の玉井仁さんは、人が持つ行動パターンや考え方のクセ、現代人の生きづらさについて考察した著書『私、合ってますよね?』でこのように述べています。
出典:『私、合ってますよね?しちゃう、できない、やめられないの正体』
人の心は相反するものが同時に存在し、いつも天秤のように絶妙なバランスをとっていますが、そのバランスはとても繊細。何かの拍子に均整が失われると極端な反応が生じます。人を信用できない人についても同じことがいえます。中には、いまひとつ自分自身に対する信頼感を持てないことに悩む人も――。
前掲書
すべての意思決定は自分でやっているのですから「自分を信頼できない」とは矛盾しているようにも思えますが、自己評価が下がっていたり、大きな決断を前に迷ったり不安を強く感じるタイミングでは、多くの人が経験する感覚でもあります。
人を信用できない人の特徴とは?
それでは、人を信用できない人に表れやすい特徴を見てみましょう。
常に警戒心が強い
人を信用できない人は常に緊張状態にあり、内心は野生の小動物のようにびくびくと周囲を警戒しています。とにかく、自分を守ることに一生懸命で、何か攻撃を受けたら、すぐに身を守れる(逃げる/反撃する)ように準備しているので、他人の言動に対しても敏感です。
過去のトラウマを引きずっている
3歳くらいの小さな子供が「これをしたら誰かに迷惑がかかるかな?」などとは考えず、自分のやりたいことや欲しいものを主張するのは自然なこと。周囲に配慮できるようになるのはもう少し後で、親などの保護者に守られながら「やっていいこと」「いけないこと」を時間をかけて学んでいきます。
しかし、家庭環境に問題を抱えているなど、のびのびと子供らしくいられない環境で育つ子供もいます。幼少期から気を張って頑張っているような状態が続くと、大人になって環境が変わっても、他人に対して心を許すことのハードルが上がってしまいます。
物事をネガティブに捉えがち
人を信用できない人は物事を悲観的に考えるクセがあり、ペシミスト(悲観主義者)になりやすい傾向があります。人を疑う心が強いため、他人の好意や褒め言葉も言葉通りに受け取ることができず、「何か裏があるのでは?」と考えてしまいます。
素直な感情表現が苦手で「ありがとう」や「ごめんなさい」などの言葉を伝えるのに時間がかかります。決して感謝や謝罪の気持ちを持っていないわけではないのですが、それをどう伝えたらいいか、わからないのです。そのため周囲から「あの人は思いやりがない」と勘違いされてしまう恐れがあります。
自分の弱みを見せたくない
野生動物は警戒心が強く、病気やけがをしていてもそれを隠そうとすることがあります。周囲に弱っている姿を見せると襲われるためですが、人間の中にも野生動物のように自分の弱いところを見せるのを極端に嫌がるタイプの人がいます。
集団生活において、ほどよい自己開示はお互いの心の距離を縮める効果があります。会話の流れで本音を打ち明けられると、なんだか親しくなったように感じるものですし、人間関係を築く上で「それくらい心を許している」という意味合いもあります。逆に人を寄せ付けず「絶対に弱みを見せまい」と頑なな態度を続けていると、集団になじもうとしない人と見なされて、孤立してしまう可能性があります。
他人のミスや欠点を許せない
不信感や警戒心は他人との関係性にも大きく影響します。人を信頼できない人は「この人物は信用に値するか?」と考えながら人と向き合うことが多く、「まず疑う」「簡単には心を許さない」という姿勢が身に付いています。
本人はうまく隠しているつもりでも、そのような心の動きは不思議と相手に伝わります。他人から不信感を向けられて心地いいと感じる人はいませんから、人間関係がギクシャクする原因にもなりかねません。

人を信用できなくなってしまう要因
人を信用できなくなってしまう理由には生まれ持った要素も関係していますが、幼少期の環境や愛着の問題が影響していることも少なくありません。
過去の裏切りやトラウマ
親しい人に嘘をつかれたり、裏切られたりしたという体験が原因で人を信じられなくなった人もいます。相手を深く信頼していただけにショックが大きく、「もうあんな思いはしたくない」と考えて心を閉ざし、立ち直るのにも時間がかかります。
幼少期の環境
「信用」とか「信頼」という言葉は、どこかふんわりと包まれるような響きがあります。先述の玉井さんは、そのような温かな感覚が持てない人は、幼少期の環境も大きく影響しているといいます。
緊張が抜けないと、過剰に相手に合わせたり、その反対に相手に対して好戦的な態度を取ったりする傾向が高まります。心や身体の力みはさまざまな形で表れるのです」
前掲書
厳しすぎるしつけを受けたり、逆にネグレクト状態まで放っておかれたりするなど、子供にとって不適切な環境で育つと、大人になっても「人を信頼できない」というかたちで残ってしまうのです。
自己肯定感が低い
自分に自信がない人は「どうせ裏切られる」「自分は助けてもらえない」と感じています。そのため助けが必要な場面でも、人に頼ることができずに苦しい思いをした体験が頭に残り、さらに周囲への不信感を強めるという負のループに陥りがちです。
また、恋愛関係でよくあるのが「自分を好きになってくれる人を大切にできない」という悩みです。自己肯定感の低い人が相手の好意を素直に受け取ることができず、試すような行動をしてしまうのは、無意識に「本当の自分を知ったら嫌いになるはず」と考えているから。自分が傷つかないための予防線を張っているのです。
SNSの影響
インターネットやSNS上には、偏った情報や真偽不明な書き込みが氾濫しています。その中から正しい情報を見つけ出すためには、ある程度の警戒心は必要です。ただそういった情報に触れるたびに「何か裏があるんじゃないか?」と疑っていては、心が疲れてしまうでしょう。
過去の経験を美化しすぎる
学生時代に築いた人間関係や思い出は人生の宝物ですが、時に新しい関係を築く際の枷(かせ)になることがあります。「あの人のような人でなければ信頼できない」と思い込み、「あんなに理解してくれる人はもう現れないかもしれない」と考えて、新しく出会った相手に心を許せないのです。
十代などは学校や教室で過ごす時間が長く、友達との信頼関係をじっくりと築くことができますが、社会人になるとそうはいきません。大人になってからの友達関係には学生時代とはまた違う魅力もありますから、どこかでそれに気づくことが大切です。
人を信用できないと仕事に支障が出る?
どんなに優秀な人でも1人で完結できる仕事は意外と少ないものです。他人に仕事を任せることができないと、すべてを自分で抱え込むことになり、負担が増えて自分で自分の首を絞める結果になります。そのような人はマネジメントには向いていません。
部下に仕事を任せたにも関わらず執拗に確認したり、口を出したりしていると相手のモチベーションが下がってしまいます。相手を信頼してある程度の裁量と選択権を渡すことで、初めてその仕事を「自分ごと」として取り組んでくれるのです。
人を信用できないと恋愛に支障が出る?
恋愛関係になると人は無防備にならざるを得ません。近づけば近づくほど、お互いに素の部分を見せる必要があるからです。恋愛の始まりの段階では相手が求める理想像を演じたり、緊張したりするものですが、一緒に過ごす時間が増えるにつれてだんだんと2人でいることに慣れていきます。
「恋愛はタイミングがすべて」ともいわれますが、警戒心が強い人はこの段階にいたるまでに時間がかかり、気持ちが近づくチャンスを逃してしまうことも……。仮に恋愛成就しても、些細なことから相手の人間関係が気になって束縛してしまうなど、「人を信用できない」という問題はなかなか根深いものがあります。
人を信用できないことはメリットにもなる?
こと人間関係においては課題もありますが、簡単に人を信用しないという性質は悪いことばかりでもありません。そのようなタイプの人は相手が信頼に値する人物かを見極める「観察眼」や物事の本質をとらえる「洞察力」に優れていることも少なくありません。
簡単にだまされにくい
人を信用できないタイプの人は、ふつうの人よりも警戒心が強く違和感や変化に敏感。感情に流されることなく、冷静に事実と向き合うという姿勢が身に付いています。
人に褒められれば「代わりに何かお願いしたいことでもあるのかな?」と考え、うまい話があっても「裏があるのではないか」と疑う人ですから、そう簡単にはだまされません。その不信感のせいで生きづらいところもありますが、石橋を叩いて渡る慎重さが身を守ることも。
自立した思考を持てる
物事に対して「まず疑う」という姿勢はクリティカルシンキング(批判的思考)の基本でもあります。多くの人がそうであるように「そういうものだから」「常識だから」といって前例踏襲を繰り返しているだけでは、それ以上のものを生み出すことはできないでしょう。
固定観念や先入観にとらわれず、自分の目で見たものしか信じないというのは、物事を深く分析し客観的にとらえようとする研究者やジャーナリストの視点にも似ています。
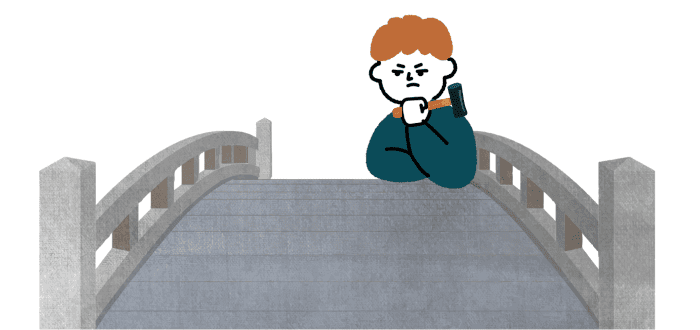
人を信頼できないことを治す方法とは?
とはいえ、ずっと肩の力が抜けずに緊張している状態はつらいものです。また、そのような態度は知らず知らずのうちに、周囲の人を寂しい気持ちにさせてしまっているかもしれません。最後に不信感から抜け出すための方法や考え方についても考えてみましょう。
信頼は小分けにする
前出の玉井さんは、「最初から大きな信頼を目指さずに、小さい信頼を積み上げてみよう」と勧めています。
前掲書
玉井さんは「人を心から信頼するということは、そんなに簡単なことではありません」といいます。ゼロか百かという極端な思考にならず、徐々に積み上げていことが大切なのです。
過去の経験を整理する
もし、自分自身の中にある他者への不信感を払拭したいと考えていて、その原因が過去のある出来事にあると分かっているのならば、その出来事を振り返って整理することが第一歩につながります。
そのために気持ちを書き出したり、日記を書いたりする習慣も効果的ですが、ときには心理カウンセラーや地域の相談窓口などに頼ってみましょう。専門家の納得感のある説明が問題解決の近道になることもあります。
自己肯定感を高める
人のことを信頼できないと悩む人が「自分のことも信頼できない」というケースは少なくありません。そうして生まれた“信頼されない自分”というセルフイメージは自己肯定感を著しく下げます。
玉井さんは本の中で「それはひっくり返すと、『本当は自分を信頼したい』『誰かを信頼できる自分になりたい』ということでもあります。それほど人は『信頼』という感覚を自然に、かつ大切に感じているのです」と伝えています。そんな自分に気づいた人に対してもこのようなアドバイスを送っています。
前掲書
まとめ
人生において信用や信頼は大きなテーマのひとつ。赤ちゃんと母親的存在の関係に始まり、幼い頃の友達関係、大人や社会人としての人付き合い、結婚なども、人と人がつながって信頼を育み、さらにそれを広げていく取り組みといえます。人を信用できないことに悩む人は、自分の問題の背景について堀り下げ、少しずつ信じる経験を積み重ねることで、より生きやすくなるはずです。

\ この記事の監修者 /
ニューモラル 仕事と生き方ラボ
ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。
ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。
人を信用できない人の特徴とは?克服する方法も解説に関するおすすめ書籍はこちら
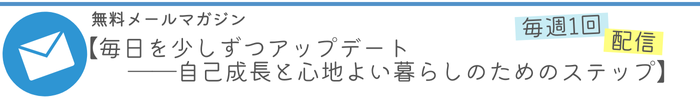


↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)
関連する投稿
-

2025年12月19日
-

人付き合いが苦手な人の6つの特徴とは?原因や克服方法についても解説
2025年08月22日
-

人と関わりたくないと感じるのはなぜ?原因や対処法について解説!
2025年07月30日
-

2025年07月15日
-

人のせいにしてしまう人の心理状態とは?特徴や対処法について解説
2025年06月19日
-

誰もわかってくれないと思ってしまうのはなぜ?要因ややわらげる方法を解説
2025年06月09日
人気ブログ
-

2024年08月14日
-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介
2024年05月29日
-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介
2024年02月21日
-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介
2024年02月09日
-

2024年01月24日
-

2024年01月13日
-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介
2023年12月20日
-

2023年12月11日
-

2023年10月31日
-
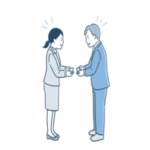
礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー
2023年10月13日

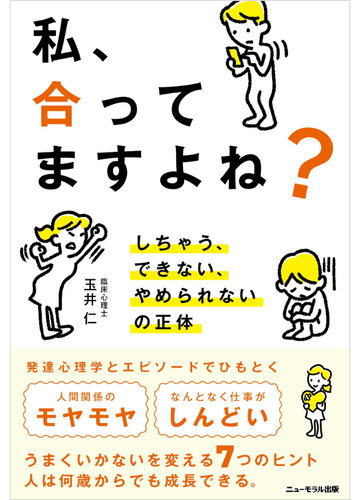
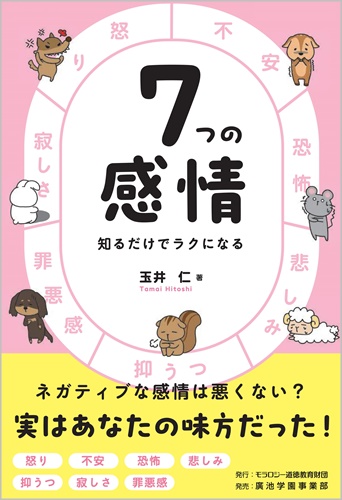
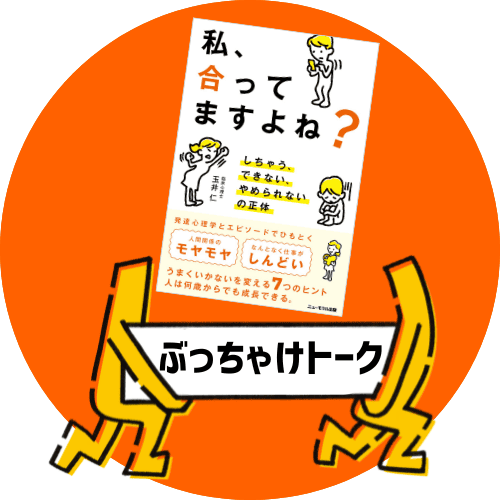









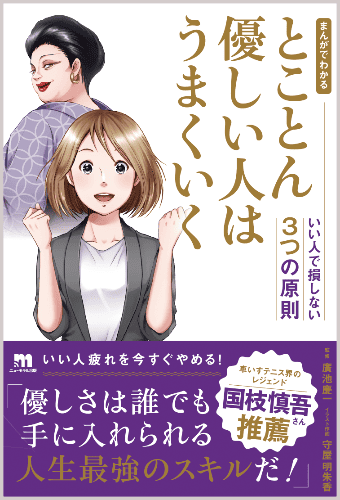
![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)
![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)