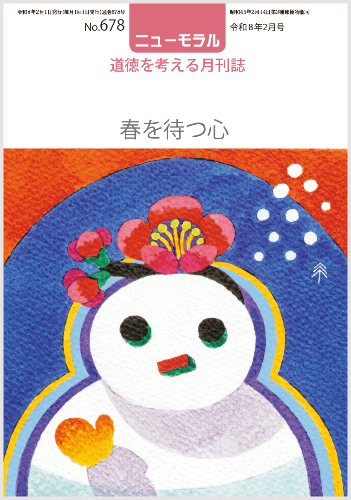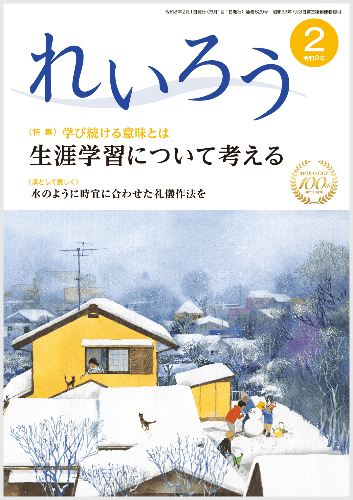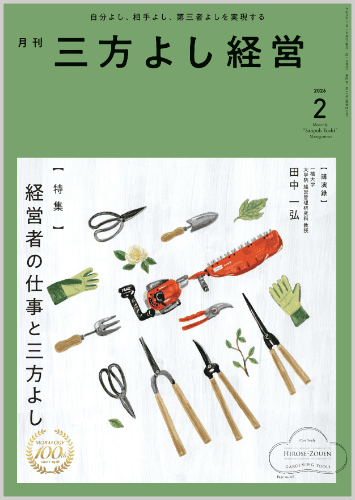友達関係に疲れてしまう根本的な原因とは?無理なく関係を続けるため大切なこと
公開日:2024年06月15日
更新日:2025年06月19日
一緒に出かけたり、趣味に興じたり、身近な悩みを相談し合ったり……。お互いがお互いを必要としながら同じ時間をともに過ごすのが友達ですが、なぜかその関係に気持ちが疲れてしまうことがあります。根本的な原因や、疲れない人間関係を築くヒントをお伝えします。
目次△▼△
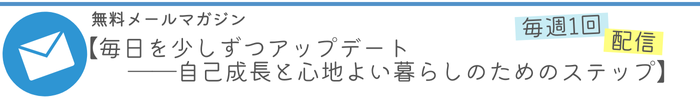


友達関係に疲れる原因とは?
本来ならリラックスした付き合いである友達関係ですが、いくつかの要因が積み重なった結果として、「しんどい、もう疲れた……」となってしまうケースが多いようです。まずは根本的な原因を探ってみましょう。
1.友達なのに気を使い過ぎている
相手に嫌われまいと友達に対して必要以上に気を使ってしまう人がいます。
友達の反応を気にして言葉を飲み込んだり、先回りした行動をとったり「私のことはいいから〇〇さんが決めて」と自分のことを後回しにして相手の希望を優先させるなど、他人優先の感覚がクセになっているのです。
心に余裕があり、本人がその状況を楽しんでいるのなら問題ありませんが、いつも他人の気持ちばかり優先しているとストレスがたまり、そのうちに「なんで自分だけ……」と不公平感を抱くもの。
対等かつ自然体で付き合えるのが友達なのに、片方だけが負担を強いられる関係は長くは続きません。
2.価値観の違い
学生時代の友達がかけがえのないものといわれる理由のひとつに、人生の早い段階で出会った相手との「利害関係を抜きにした関係性」があげられます。
大人になってから会社や社会人サークルなどで出会う人々は、仕事や経済的状況などの似た相手が多くなりがちですが、小学校や中学校などのクラスメイトは自らで選んだメンバーではありません。
ある意味では“たまたま”そこにいた者同士、教室という空間で同じ時間を過ごして深い信頼関係を築き、相手と自分の違いを無条件に受け入れる大切さ、そして集団生活で生きる術をともに学びます。
しかしながら、それぞれの持つ価値観や目指す方向性などがお互いに受け入れられないレベルで決定的に異なると、徐々に関係がうまくいかなくなることがあります。初めは同じ方向を向いていたけれど、途中からすれ違うようになった……という場合もあるでしょう。
特に、10代後半から20代前半は進学や就職を控え、自分が何者であるかを考えたり、さまざまな価値観を吸収したりする「変化の多い時期」ですから、人として大きく成長するタイミングでこれまでの友達関係にも変化が起こるのは不思議なことではありません。
3.時間の使い方の違い
自分の時間を犠牲にしてまで友達と過ごす必要はないのに、約束を断ることで相手に嫌われるのを恐れて「ノー」が言えない人がいます。
他人の都合ばかりに合わせていると自分の時間が取れず、勉強や趣味などにひとりでじっくりと取り組む時間がなくなります。どうにか時間を確保できたとしても、細切れで集中できない場合もあるでしょう。
友達と会う予定をおっくうに感じているのなら、もしかしてそれは時間の使い方やスケジュールを立てる際の「優先順位」を間違っているのが理由かもしれません。
4.期待と依存
どれほど仲がいいからといって、友達は常に「一心同体」ではありません。自分のペースを考慮せずに過剰な期待や依存をされると、誰しもプレッシャーを感じるもの。
期待や依存を“された側”の視点で考えてみると、最初は少し無理をして頑張ってみるかもしれませんが、そのような状況が続くと気疲ればかりが増えていき、いつか限界を感じて相手から離れたくなります。
一方の“していた側”からすれば、友達が無理して自分の要求に応えていたことには気づいていませんから、「これまでは応じてくれていたのに……」と不満を抱きます。そんなふうに片方が片方に寄りかかる関係性は友達として健全とはいえません。
親しい関係性に甘えて「こうしてくれるだろう」「言わなくてもわかるはず」と必要な言葉を省くのも誤解やすれ違いの原因になります。
5.連絡の頻度に差がある
多くの人がスマホを持ち歩き、SNSやチャット機能など双方が求めればいつでも気軽につながれる時代です。それ故にあまりに頻繁な連絡や長時間の会話が続くと、「しんどい」と感じることも珍しくはありません。
人はそれぞれ心地いいと感じる連絡の頻度が違いますから、お互いにそれがマッチしていないと片方が疲弊したり、不満を抱いたりする原因に……。
人によっては連絡の頻度が「多すぎる」と感じても、相手の気分を害するのが怖くて、正直な気持ちを伝えられなくて我慢している人もいるかもしれません。
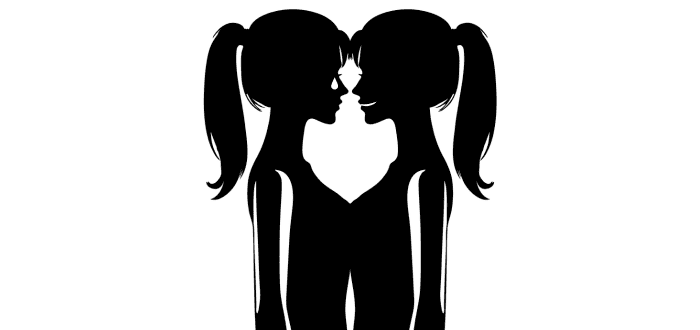
友達関係で疲れてしまった時の対処法5選
それでは友達関係で疲れてしまった時、どうすればいいのでしょうか?
1.距離を置く
友達関係を「なんとなく疲れた」と感じているのなら、まずはその友達やグループと一時的に距離を置き、ひとりで考える時間を確保しましょう。一旦、離れることでお互いの関係や自分自身の気持ちを冷静に見つめなおすことができます。
離れることでホッとひと息つける人もいれば、逆に友達の大切さを以前よりも大きく感じる人もいるでしょう。そこで改めて自分にとって大切なこと、必要なことをじっくりと考えてみると、これからどう動くべきかが見えてくるはずです。
2.正直な気持ちを伝えてみる
無理をしていることや疲れていること、現在の自分の気持ちや状態を言葉にして友達に伝えてみませんか?友達が本当にあなたのことを思っているのなら必ず理解してくれます。
今後も関係を続けたいと考えているならば、相手を直接的に否定するような言葉は避けておきたいものです。なるべく「わたし」を主語にして、「いま少し疲れていて、メールの返信が遅かったりしても気にしないでね」とか「気持ちが落ち着いたら連絡するよ」などと具体的な状況と期間を伝えておくと、相手も不安にならずに済みますし、きっと友達としてできることを考えてくれるでしょう。
気持ちを打ち明けて、それを拒否されたのなら……。その相手もまた、人のことを思いやる心の余裕がないのかもしれません。すぐに元の関係に戻るのは難しいかもしれませんが、もしも「本当の友達」なら、いつかまたお互いを理解する機会がめぐってくる、と考えましょう。
3.人間関係は「変化する」と考える
本来、友達という枠組みの中での人間関係や付き合いは出入り自由なはず。ですから、すべての人付き合いに対し、同じように時間や熱量を注ぐ必要はありません。
ひとりの友達と長きに渡ってじっくりと付き合う人もいれば、その時々で隣にいる友達が変わる人もいるでしょう。どちらが良い悪いではなく、あくまで「人間関係のスタイルが違う」というだけです。
人間関係のバランスや優先順位は常に変化するものと考え、自分が自然体でいられる人間関係のあり方を探ってみましょう。
4.リフレッシュする
友達との関係は以前と変わらないのに、なぜだか「自分ひとりだけが疲れている」状況の場合、ちょっとした気分転換をするだけで改善することがあります。
趣味に没頭したり、自然の中で過ごしたりして心に余裕ができると、内側からエネルギーが湧いてきます。すると、少しくらい嫌なことがあっても気にならなくなり、思い悩むことも減ってきます。
同じような状況に直面してもネガティブ側に取り込まれてしまう人とそれをポジティブにとらえられる人がいます。病気に対する抵抗力が人それぞれ違うように、心にも“体力”があるとしたら、すぐには折れないしなやかな心を目指したいですね。
5.第三者に相談する
気持ちが疲れすぎていると頭が働かなくなります。特に「自分のこと」となると、なかなか冷静な判断ができないものです。そのような時は、家族やスクールカウンセラーなどの信頼できる第三者に相談し、客観的な意見を得るのもひとつの選択肢です。
もしも、相談する相手が年上であったら「僕は学生時代にこんなことがあってね……」と両親や先生の過去のエピソードを聞けるきっかけになるかもしれません。
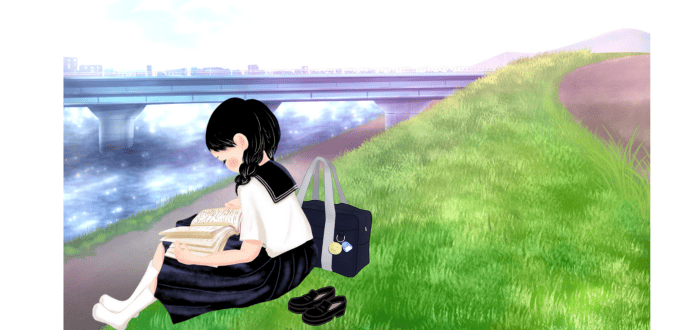
長く続く友達関係を築くためのヒント
現時点では「友達関係に疲れた」と感じても、縁あって友達になった相手です。お互いに無理をせず大人になってからも長続きをする関係を築くためには、どのようなことを意識したらいいでしょうか?
1.お互いの価値観を尊重する
関係を長続きさせるためには、お互いの価値観を尊重し合うことが何よりも大切です。学生時代は同じ教室で過ごした友達も、卒業や進学、就職をきっかけにそれぞれの進路を歩み始めます。ある意味、そこからが友達関係の第2のフェーズです。
友人関係はお互いの環境が変わったタイミングで関係が切れてしまうことも少なくありませんが、立場や肩書など関係なく付き合える相手こそが「本当の友達」。相手の意見や感情を理解し、それを受け入れる姿勢を失わなければ、一度築いた信頼関係がなくなることはありません。
友達は数が多ければいいというものでもありません。心理カウンセラーの長谷静香さんは、著書『周りを優先し過ぎるお疲れママのためのご自愛レッスン』の中で、心の奥底を打ち明けられる親友は「たった一人でもいい」といいます。
「交友の関係をよりよくするために大切なのが、『相互尊敬』『相互信頼』です。『相互』という言葉が前についているのがポイント。どちらが上とか下ではなく、勇気づけ合える関係。そして、お互いに相手を尊敬し合い、深く信頼し合う関係」
「違いを認め、礼節を持って接するのが尊敬です。より先により多く、ひとりの人格ある人間として相手を尊敬します。そして、信頼というのは信用とは違い、根拠がなくとも無条件に信じ続けることです。そのような深い絆で結ばれる友達は、親友とも呼べますね」(同書より)
2.程度な距離感をキープする
友達関係を長く続けるためには、ほどよい距離感を保つことを忘れないようにしたいものです。かつては四六時中一緒にいた相手でも、大人になってからもそれを続けるのは無理があります。
成長する過程で人間関係においての「必要な距離感」を学び、過度に依存しすぎず、お互いに自立した関係を築く方法を知っておけば、自分にも相手にも無理のない人付き合いが自然とできるようになります。そうした人間関係のスキルは社会人になってからも、会社や家庭で大いに役立ちます。
3.定期的に「新しい思い出」を上書き
学生時代に長い時間を過ごした相手とは会うたびに思い出話が弾みますが、できれば定期的に“新しい思い出”を上書きしたいもの。定期的に集まってお互いの近況を伝え合ったり、週末にちょっとした小旅行を企画したりするのもお勧めです。
学生時代の思い出はかけがえのないものですが、就職や進学、結婚、子育てなどで生活が大きく変化するタイミングに入ると、会話のトピックスだけでなく、お互いが求める「友達付き合いのあり方」も変わっていきます。現在進行形のフレッシュな友達関係をキープするよう心がけると、それぞれが置かれた立場や環境がどんなに変わったとしても、揺るがぬ友達関係を築くことができます。
物理的に離れてしまった場合は、気軽に会うことはできなくても、Keep In Touch(連絡を取り合うこと)を意識してお互いの記念日を祝い合うなど、つながりをなくさないよう心がけましょう。
まとめ
お互いに心を許し、楽しい時間をともに過ごす相手である「友達」ですが、片方が気を使いすぎたりや距離感を間違えてしまうと、逆に親しい関係が心の負担になることがあります。無理のない付き合いを続けるためには、まずは何が負担の原因になっているのかを考えてみましょう。
学生の時に出会い、大人になっても関係が続く友達は唯一無二のもの。かけがえのない存在として大切にしたいものです。

\ この記事の監修者 /
ニューモラル 仕事と生き方ラボ
ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。
ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。
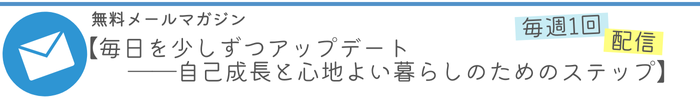


友達関係に疲れてしまう根本的な原因とは?無理なく関係を続けるため大切なことに関するおすすめ書籍はこちら
↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)
関連する投稿
-

2025年12月19日
-

人付き合いが苦手な人の6つの特徴とは?原因や克服方法についても解説
2025年08月22日
-

人と関わりたくないと感じるのはなぜ?原因や対処法について解説!
2025年07月30日
-

2025年07月15日
-

人のせいにしてしまう人の心理状態とは?特徴や対処法について解説
2025年06月19日
-

誰もわかってくれないと思ってしまうのはなぜ?要因ややわらげる方法を解説
2025年06月09日
人気ブログ
-

2024年08月14日
-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介
2024年05月29日
-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介
2024年02月21日
-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介
2024年02月09日
-

2024年01月24日
-

2024年01月13日
-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介
2023年12月20日
-

2023年12月11日
-

2023年10月31日
-
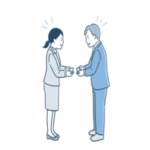
礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー
2023年10月13日

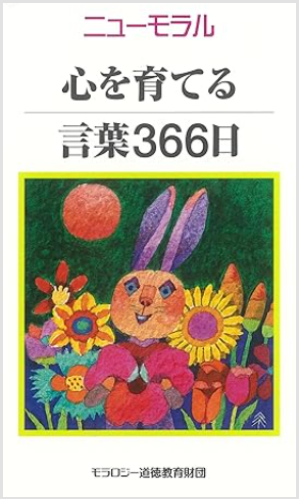










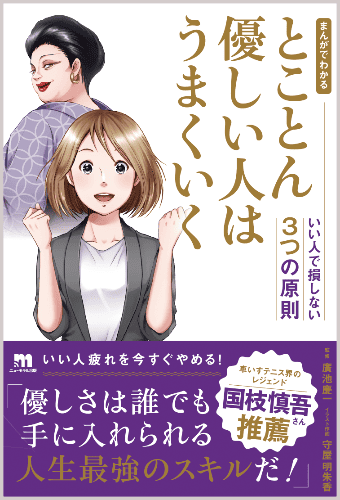
![私、合ってますよね?-しちゃう、できない、やめられないの正体_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1308_500_1.png)
![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)
![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)
![7つの感情‐知るだけでラクになる_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1151_7tunokannjou500_01.jpg)