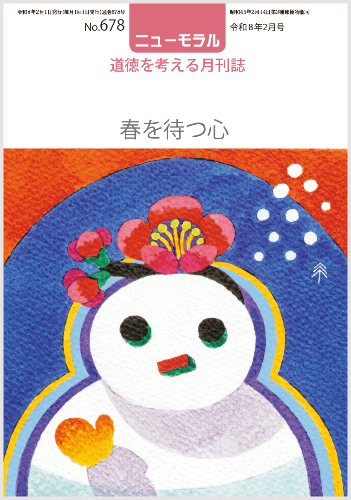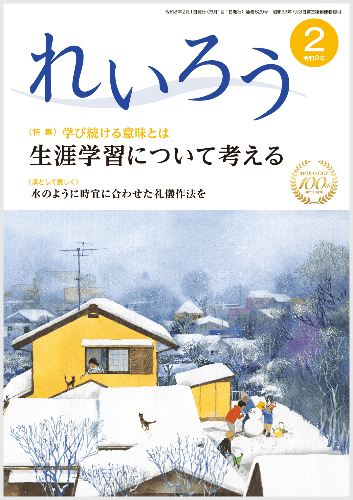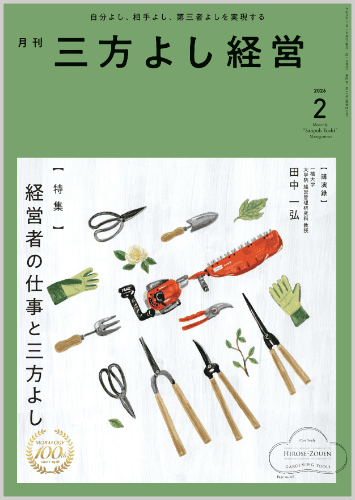毎日が楽しくない、人生がつまらないと感じる理由は?楽しい日常を取り戻す方法を紹介
公開日:2024年05月16日
更新日:2025年09月19日
日々の生活が楽しくないと感じたり、明日が来るのをおっくうに思うことはありませんか。365日を毎日元気いっぱいで過ごす人も珍しいですが、先の見えない憂鬱(ゆううつ)な気持ちが長く続くのはつらいものです。原因は自分の中にあるのか、それとも外にあるのか?つらい状況を引き起こす要因を知れば、少しだけ気分が晴れるかもしれません。
目次△▼△
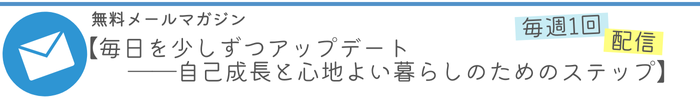


人生がつまらない、毎日楽しくないと感じる理由
まずは、人生がつまらない、毎日楽しくないと感じる理由を考えてみましょう。
単調な日常への不満
大きな変化や刺激に欠けていたり、固定されたルーティーンに囚われすぎていたりする日々を送っていると、生活から新鮮さが失われて物事が単調に感じられるようになります。俯瞰してみれば小さな変化や楽しい出来事も必ずあるはずですが、それらに目が向かなくなってしまうのです。これが長期間続くと、毎日をつまらなく感じる原因になります。
目標や目的がない
明確な目標や目的がないと、何のために日々を過ごしているのか、わからなくなることがあります。「糸の切れた風船のよう」とでも表現すればいいでしょうか。人生には誰しもそんなタイミングがあるもので、一時的にふわふわと宙を漂う状況を楽しんでしまえばいいのですが、それがうまくできる人は多くないかもしれません。
こうして気持ちの切り替えができないまま、自分の人生が「退屈で無意味」に感じ、ますます無気力になってしまうのです。
理想と現状が一致しない
仕事で割り当てられた業務やイメージしていた大学生活と日々とのギャップなど、その人の価値観や興味の方向性が「現実の状態」と一致しない場合、何をやっても満足感や達成感が得られず、目の前の日常を楽しめないことがあります。「自分はここにいるべき人間ではない」と不満を募らせ、それが叶わないとわかると糸が切れたようにやる気がなくなってしまうのです。
理想と現状が一致しないケースの一例ですが、出産後の女性の多くは自分中心の生活から突然、赤ちゃん中心の生活になります。最近は男性が育児のメインを担うケースもあるでしょう。どちらにせよ新生児は目が離せませんから、これまでの生活とのギャップに戸惑いながらも家族で力を合わせ、なんとか生活を回していくことになります。
そのような状況で「こうありたい」理想の自分と、「いまここにいる」自分を同じレベルにすることは容易ではありません。子供の成長にともない、次第に折り合いをつけられるようになりますが、モヤモヤとした気持ちを引きずったまま、「毎日が楽しくない」と悩んでしまう人は少なくありません。
対人関係のストレス
学校や職場などでの対人関係に問題があったり、日常的に接する人物に苦手意識を持っていたりすると人とのコミュニケーションが苦痛になります。ひとつひとつは小さくても、それが積み重なるとかなりのストレスです。ストレスがうまく解消できないままでいると、被害妄想に陥ったり孤独感を募らせたりして、「誰も私のことを助けてくれない」「やっぱり人生は楽しくない」と思い込んでしまう可能性があります。
ネガティブな思考パターン
悲観的な考え方が定着すると、そこから抜け出すのはなかなか困難です。ポジティブな言葉や出来事さえもネガティブに捉えて、他人に攻撃的になったり自らを過剰に否定してしまったりするのです。気持ちがネガティブ側に寄りそうな感じがしたら、できるだけその原因からは距離を取るようにしてください。休暇を取るなど、リラックスして心身を休ませる時間も必要でしょう。
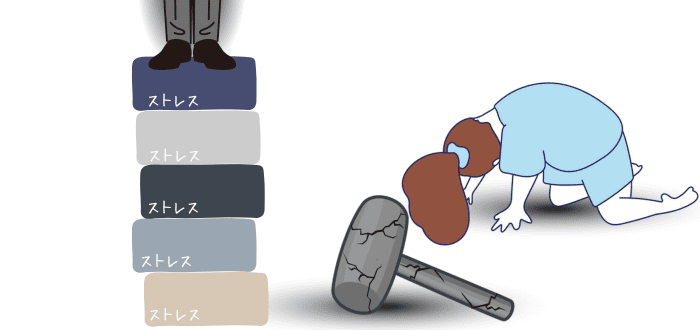
人生がつまらない、毎日が楽しくないと感じる人の特徴
それでは、毎日が楽しく感じられない人にはどのような特徴があるのでしょうか。
自己効力感が低い
自己効力感とは、課題を前にして「きっと大丈夫だ」「自分ならうまくいく」と思えることです。根底に自分に対する信頼と自信があるので、物事や人間関係に対しても積極的に行動できます。一方で自己効力感の低い人は、小さな悩みや問題を実際よりも大きく感じてしまう傾向があります。
また、自己効力感が低いタイプの人は新たな挑戦に苦手意識があり、失敗を恐れて自分自身が確実にできることだけを繰り返しがちです。固定されたルーティーンの中で新しい楽しみを見出すのは難しく、そんな毎日に満足できずに「つまらない」と感じてしまうのです。
目標や情熱がない
何か大きなことを成し遂げたあと、せっかくハードワークから解放されたのにポッカリと穴が開いたような気分になった経験はありませんか? 目の前にわかりやすい目標がないと、毎日が単調で意味のないものに感じられることがあります。物事を始める前に具体的な目標を立てたり、それを達成することに意味を見出したりするような、生真面目なタイプの人が陥りやすい現象です。
また、仕事や生活に忙殺される中で、かつて自分が好きだったものや情熱を注いでいたものから離れ、ふと「一体、何のためにがんばっているのだろう」という思いが浮かび、力が抜けて無気力になってしまう場合があります。
孤立感を抱いている
家族や友人などの近い関係だけではなく、同僚や同級生、近所の人たちなど、さまざまな濃淡の人間関係がある中で、何気ない会話のやり取りは毎日に刺激を与えてくれます。
しかしながら、社交的でなかったり対人関係に苦手意識があったりする場合、人との交流を避けてしまい社会的な孤立や孤独を感じやすくなります。自分自身とじっくり向き合う時間も大切ですが、人と関わらないでいると考え方が偏りがちになります。実際は心配してくれる人がたくさんいるにも関わらず、自分が置かれた状況を悲観して、孤独と不満を募らせてしまうのです。
毎日を楽しむための考え方とやるべきこと
ビジネスコンサルタントの三枝理枝子さんの著書『幸せを感じる人間力の高め方』(モラロジー道徳教育財団)から、一節をご紹介します。
「迷い、裏もあり、失敗もするのが人間です。生きていると出合う不安、蓋をしておきたい醜い部分、足りないところ、これらは見て見ぬふりをして生きていくこともできるでしょう。しかし、希望も迷いも、表も裏も、成功も失敗もあることをすべて受け容れ、立ち止まったり、葛藤し、転びながらも生きていくのが人間です」
出典:幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]|ニューモラルブックストア
毎日が楽しくないと感じている人が自分自身を責める必要はまったくありません。より高く飛ぼうとするのなら、一旦深く踏み込む必要があります。ここに毎日を楽しむためのいくつかのアイデアを紹介するので、できることから取り組んでみませんか?
新しい趣味を始める
停滞した日常から離れるひとつのきっかけには、新しい趣味がぴったりです。いつかやりたいと思っていた習い事でもいいですし、流行りの“推し活”でどっぷりと好きな世界観に没入すれば、いつもと同じ景色が少し違って見えるかもしれません。もしも時間とお金が許すなら、気ままな小旅行の計画を立てるのも気分転換になります。
目標を設定する
短期的なものと長期的なもの、それぞれの目標を設定してみましょう。実現できそうなレベルの目標を設定すれば、小さな達成感を積み重ねて自信につなげることができます。長期的な目標は日々の生活に意味と方向性をもたらし、モチベーションを保つのに役立ちます。
人間関係を育む
知り合いは多ければ多いほどいい、というものではありません。自分を心から理解してくれていると信じられる相手が1人いるだけでも心の支えになります。人とのつながりに感謝して、普段から大切にしたいものです。
ときには自分と異なる考え方やバックボーンを持つ人と交流すると、今まで自分が閉じこもっていた世界がいかにせまかったかと気づかされます。「なぜ自分はこんなことで悩んでいたのだろう?」と背中を押されるはずです。
自己成長に投資する
多くの人は学校を卒業した後は仕事や家庭が中心になり、どうしても自分のことが後回しになりがちです。少し落ち着いたタイミングで、仕事に役立つ資格の取得でも趣味のスキルアップでも構いませんから、自分自身の学びに時間とお金を投資してもいいかもしれません。なんとなく過ごす日々に新たな目標が生まれ、モチベーションが高まります。
周囲に「ここからここまでの期間は勉強する!」と宣言して、学びに没頭する時間を意識的に作るのもお勧めです。自分に対しても、「皆に宣言したのだから、結果を出そう」とほどよいプレッシャーをかけられます。身に着けた知識やスキルは自身の可能性を広げ、現状から脱却する大きな手助けになります。
ポジティブな思考を持つ
同じ状況にいても、幸せを感じる人と不満を感じる人がいるのはなぜでしょうか? 幸せを感じる人は日々の小さな喜びを見逃さず、そこにある「当たり前」に感謝できる人です。困難に直面しても感情的にならず、不都合を受け入れ、「そうきましたか」と冷静に次の手を考えられるのです。
仕事や人間関係においてのネガティブな気持ちの要因がはっきりとわかっている場合は、思い切ってそこから、一度「手をはなす」のも手です。ひとりが抜けたところで、自分が心配しているより職場も家庭も案外まわるもの。もしも状況が許すのであれば、自分の気持ちを優先したほうがいいタイミングもあります。
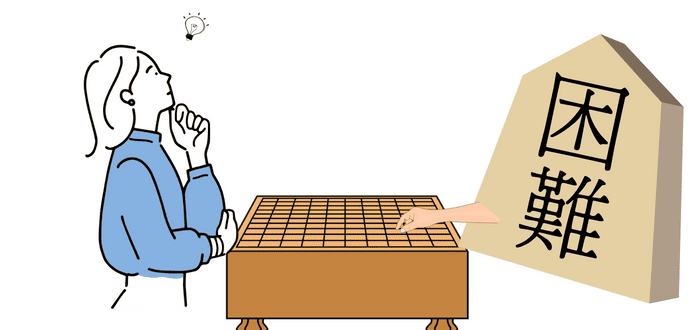
毎日を楽しむためにやらないほうがいいこと
一方で逆効果になる行動や考え方もあります。自分を必要以上に批判したり、他人と比較したりすると、自己評価がさらに低下してネガティブな感情を増幅させる要因になってしまう可能性があります。一発逆転を狙ってリスクの大きい判断をするのも避けておきましょう。
「自分のせい」「自分なんて」と考える
すべての問題の責任が自分にある、などと考えると、さらに深い淵にはまってしまいます。出来事にはさまざまな要因がありますから、「誰かひとりのせい」はあり得ないと考えましょう。また、「どうせ自分なんて」という考え方や発言は自分だけでなく、あなたを大切に思っている人たちをも傷つけます。あまり感情的にならず、「状況はいつか変わる」と考えて目の前のことに冷静に対処していれば、やがて解決の糸口がみえてきます。
過去の失敗に固執する
前出の三枝理枝子さんは、失敗について「意味があるから起きている」と受け容れると、心がスッと楽になり自分自身も納得がいくと伝えています。
「大切なのは自分自身に向き合って素直になること。自分の中に問題や苦しみを生み出している要因を見つけることです。そして起こってしまったことにこだわりすぎないことです。そんなにこだわったところで、問題が起こる前に時を戻すことはできませんし、未来に何が起こるかは誰にもわかりません」
出典:幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]|ニューモラルブックストア
失敗から学ぶことは大切ですが、それに固執していては前に進めません。いくつも事業を成功させているような経営者は、その裏でいくつもの失敗を重ねているものです。失敗したところで止まらず、うまくいくまで続けるからこそ成功を手にすることができるのです。
一発逆転を狙う
不本意な現状から脱却しようと、ビジネスなどでリスクの高い“一発逆転”を試みたくなりますが、あまりお勧めできません。明確な目標や向上心からの行動ではなく、「いまを変えたい」というだけの動機では冷静な判断ができない可能性があるからです。怪しげな儲け話に飛びつく前に、リターンとリスクをきちんと見極めたいものです。
ネガティブな情報に振り回される
人は気持ちが落ち込んでいると、現実逃避のため偏った情報に振り回されてしまいがちです。インターネット上の記事やウェブ広告は、その人の閲覧履歴などから属性を推定してカスタマイズした情報を表示しますから、ネガティブな情報に固執するとせまい世界の中だけで回遊して考え方がどんどん偏ってしまいます。そうしたウェブ広告やメディアの仕組みを知り、できるだけ正確な情報を得ることが大切です。
1日何時間もスマホでSNSを見てしまうような人は、一時的な「デジタルデトックス」を試すなどネットと離れる時間が必要かもしれません。不安感やストレスを軽減し、安心感や幸福感が高まるなどの効果があります。
閉じこもってしまう
自分の殻に閉じこもってしまうと悩みを相談する相手もいなくなり、ますます状況が悪化する可能性があります。人とあまり会いたくない気分だったとしても、これまでの人間関係を断ち切ったり相手を避けたりするのではなく、細々とでもいいのでつながりを保っておいてください。信頼できる相手ならば、「いま自分はこういう状態で、連絡をもらっても返信に時間がかかる」などと伝えておいてもいいでしょう。あなたを大切に思っているならば、きっと見守ってくれるはずです。
まとめ
ネガティブな思考を断ち切り人生を楽しむためには、自分が本当にやりたいこと、欲しいもの、会いたい人など、自らの興味や関心が向いている方向を知る必要があります。すでに停滞感をつくり出している要因がわかっているのなら、そこから一旦離れるのも有効です。
「変わりたい」という気持ちがあれば、毎日への向き合い方を変えることは可能です。日常を楽しめないという状況は長くは続かないと考えて、あまり深刻にならないことが大切です。
ただし、工夫をしても「どうしても楽しめない」「何もする気になれない」といった状態が続く場合は、心の不調が背景にある可能性も考えられます。以前は楽しめたことが楽しめなくなった、自分には価値がないと感じるなどのサインがあるときは、無理に一人で抱え込まず、医療機関に相談することも大切です。うつ病などは適切な治療や休養、カウンセリングによって改善が期待できます。

\ この記事の監修者 /
ニューモラル 仕事と生き方ラボ
ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。
ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。
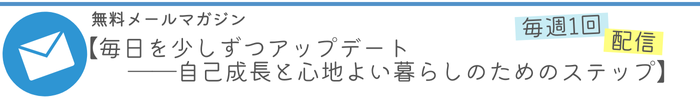


毎日が楽しくない、人生がつまらないと感じる理由は?楽しい日常を取り戻す方法を紹介に関するおすすめ書籍はこちら
以下のサイトで発信されている情報も、毎日を楽しむヒントになるでしょう。
ご興味をお持ちでしたら、あわせてご覧ください。資格を取るならフォーサイト
↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)
関連する投稿
-

2026年01月20日
-
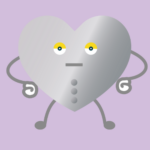
2026年01月09日
-

2025年12月26日
-

ウェルビーイングとは?世界的に注目されている理由や実現のための必要な要素を解説
2025年12月16日
-

人生楽しくない、つまらないと思うのはなぜ?抜け出すための6つの方法とは?
2025年08月02日
-

自分を変えるための方法とは?人間は自分を変えることはできる?
2025年07月28日
人気ブログ
-

2024年08月14日
-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介
2024年05月29日
-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介
2024年02月21日
-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介
2024年02月09日
-

2024年01月24日
-

2024年01月13日
-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介
2023年12月20日
-

2023年12月11日
-

2023年10月31日
-
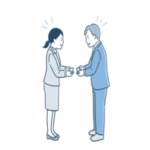
礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー
2023年10月13日

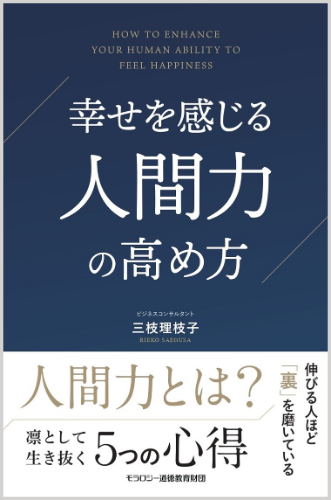









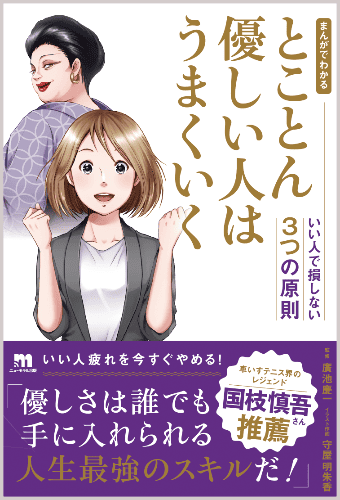
![私、合ってますよね?-しちゃう、できない、やめられないの正体_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1308_500_1.png)
![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)
![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)
![7つの感情‐知るだけでラクになる_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1151_7tunokannjou500_01.jpg)