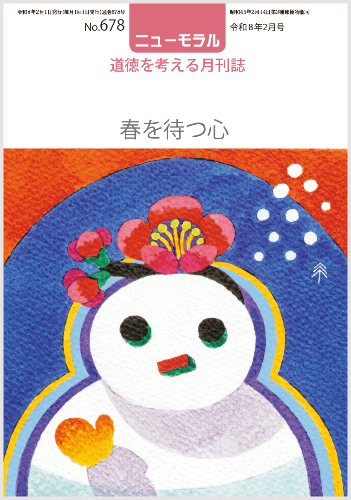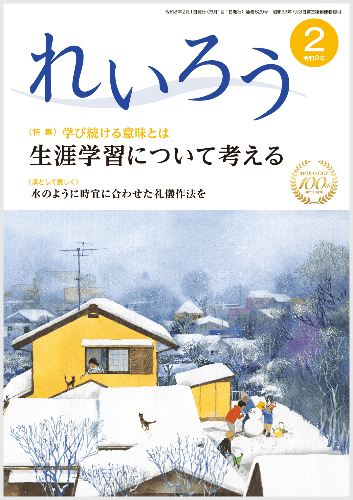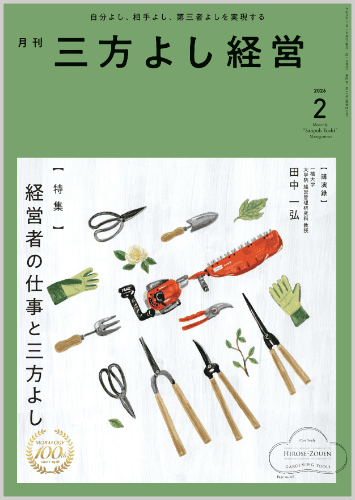「自分が正しい」と思っている人の特徴や接し方について解説
公開日:2025年04月09日
更新日:2025年10月22日
自らでやりたいことを見つけ、「こうしたい」という気持ちを持つのは大切なこと。ただ、やりたいことに取り組む中で「自分は正しい」という思いが強くなりすぎると、周囲の人だけでなく自分自身も苦しくなります。今回は「自分は正しい」が強すぎる人の特徴やその要因について考えてみましょう。
目次△▼△
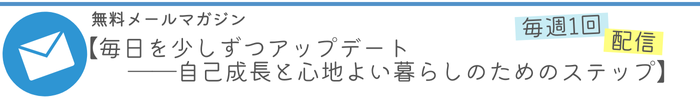


自分が正しいと思っている人の特徴とは
「自分が正しい」と考えるタイプの人には、いくつかの分かりやすい特徴があります。
自分の意見を曲げない
自分の考えや行動に対して絶対的な自信があり、周囲から違う意見が出た場合も「私の方が合っているのに」という姿勢を崩しません。他者のアドバイスを受け入れて軌道修正することを「負けた」と感じてしまうため、一度動き出した後に状況が変わると臨機応変に変化するのが苦手です。
他人を否定しがち
自分の意見が強すぎる人は、ともすると周囲の人に対して無意識に「自分のほうができる」という上から目線になりがち。ただ「自分は有能だ」と考えているだけなら何も問題はありませんが、最初から「他の人は間違っている」と決めつけて、相手を軽んじた態度をとってしまうことも……。
そんな特徴が特に強く表れるのが会議です。共通の目標を持った人々が集まり、お互いの意見をすり合わせながらより良いものを探すのが会議の目的ではありますが、このタイプは他の人が意見を発表している最中も「どう伝えれば自分の正しさを証明できるか」について考えていたりします。
経験や知識に自信を持ちすぎる
多くの知識や経験を持つがゆえに、少し気を抜くと思考が自分の都合のいい方向に偏ってしまうことがあります。「やるべきことをやってきた」という自負からか、相手の状況も考慮せず「ふつうは○○だよね」という言葉が口癖になっている人も。新しい情報や異なる意見を受け入れようという姿勢にも欠けるようです。
これまで正しいと思われていた定説が、新しい技術や研究によって覆されることも珍しくありませんから、このような態度を続けていては、いつかは時代や変化のスピードに取り残されてしまいます。
責任を他人に押し付けがち
自分の中に「いつも正しい私」という理想像があり、それが崩されるのを恐れるがために、失敗を認めるのを過剰に嫌がります。何かトラブルが起こったときも、まず「自分は悪くない、きっと他の人のせいに違いない」と考えようとする傾向もあります。
職場などのチームの中で生まれた失敗は、本来は「誰のせいか」よりもシステムやレギュレーション(規定)の問題を掘り起こし「なぜ起こったか」「どうすれば再発を防げるか」に目を向けることが大切です。しかし、このタイプの人は自分を正当化することを優先して、失敗の原因を他人に押し付けがち。その結果、周囲からの信頼を失うことも少なくありません。
感情的になりやすい
自分の正しさを証明しようとするあまり、周囲の意見を冷静に受け止められないこともあります。議論や意見交換は優劣の判断や勝負の場ではなく、反論も人格の否定ではありません。それでも自分と異なる意見を示されることを「侮辱された」ととらえて、感情的に反応してしまうのです。本人は「間違った自分を受け入れることはできない」と考えているため、これもひとつの防御反応といえます。
人間関係がうまくいかないことが多い
いつも自分の考えを押し通そうすると摩擦を生みます。人に与えたり与えられたり、時には譲ったり譲られたりしながら築いていくのが人間関係ですから、毎回決まった人の意見だけが通るような状況は、長続きしません。気づいていないのは本人だけで、すでに周囲からは「あの人はめんどくさいから近づかないでおこう」と敬遠されている場合もあります。
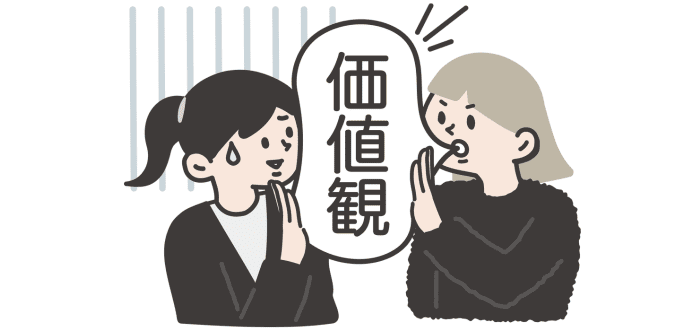
自分が正しいと思ってしまう要因
続いては「自分だけが正しい」という思考に至るまでの過程と、その要因についても考えてみましょう。
成功体験が多い
なにかと「自分が正しい」と考える人は、なんの根拠もなくその思考に至ったわけではありません。子供の頃に優等生だったり、そうでなくても人一倍に努力した経験があったりと、それなりの成功体験を積んできたがために、万能感にも近い「自分はできる」という感覚を身につけていることも……。
ただ、どれほど有能な人も「外からの意見や提案を取り入れよう」という謙虚な姿勢を失ってしまっては、それ以上の成長は見込めません。
実際、頭のいい人ほど他者の意見を取り入れることがうまいもので、投資家のウォーレン・バフェットは「自分より賢い人の意見を聞く」ことを重視し、柔軟な投資判断を行った結果として、今の成功があると伝えています。
自信が強すぎる
「自分はできる」という感覚は自らの能力を信じることであり、自分自身への信頼や自信につながります。幼少期の子供にとっては「やりたい」と感じることを見つけて、動き出すための後押しともなるポジティブな心の動きですが、それが強くなりすぎると人間関係などで摩擦が生じる原因になってしまうことも。
他人の意見を尊重せずに自分ひとりで物事を推し進めようとしてばかりいると、周囲に“尊大な人”のような印象を与えてしまいます。適度に自分に自信を持ちながら、謙虚な気持ちを忘れないでいるのはなかなか難しいですから、「できることもあるし、できないこともある。それでいい」くらいに考えておくといいかもしれません。
自己肯定感が低い
不思議なことに「自分は正しい」と強く主張する人ほど、実は自己肯定感が低いケースがあります。自分の意見を強く持っているように見えて、内心は「自信がない」ことも少なくないのです。周囲の人の意見に耳を傾けると自分の価値が否定されるように感じるため、無理にでも自分を正当化しようとしてしまうのか“勝ち負け”にもこだわりがちです。
しかし、実際のところ、すべては白黒で説明できるような問題ばかりではなく、グレーやグラデーションとして存在する割り切れないことのほうが多いのですから、そのような二元論にとらわれすぎると生きづらくなります。
そんな人は「私は合っているさん」かも?
臨床心理士の玉井仁さんは著書『私、合ってますよね?』で、人が日々を過ごす中で無意識にとらわれた行動パターンや心の癖に焦点を当て、「しちゃう、できない、やめられない」として解説しています。玉井さんによると「自分は正しい」という考えにとらわれた状態は、3歳ごろまでの幼児期前期のテーマとも重なるといいます。
出典:『私、合ってますよね?しちゃう、できない、やめられないの正体』
幼児期前期はさまざまなことに対する興味関心が高まり、自ら取り組もうとする姿勢を周囲から認められることで、さらに取り組みを進めようとする「自律心」が育つ時期。トライアンドエラーを繰り返しながら、挫折や失敗を乗り越えて成長していきます。
周囲から褒められた経験は自己肯定感につながりますが、成長するにつれて世界が広がり、自分を取り巻く周りの人たちとの関係も大切になっていきます。
前掲書
「正しい」という言葉を聞くと、なんだかそれが絶対的なものと思ってしまいますが、時代や状況によって正義の意味や価値観は驚くほど簡単に変化します。ですから、時には「正しさ」に固執せず、人の意見を柔軟に受け入れるなど、臨機応変な行動も必要になります。
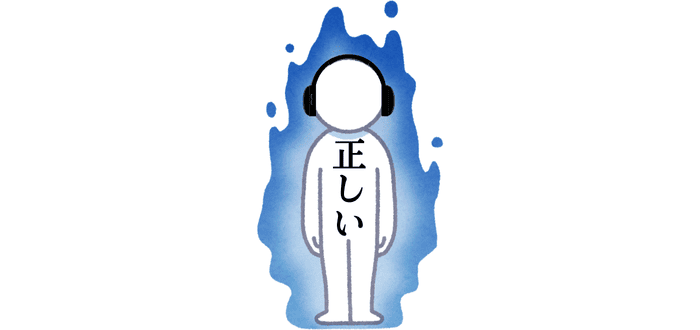
自分が正しいと思っている人との接し方
最後に家族や友達、職場の同僚など、周囲にそのような人がいる場合の接し方についてもご紹介しましょう。
否定せずに話を聞く
「自分が正しい」と信じる人に向かって、いきなり正論をぶつけたり強く否定したりすると、相手がますます意固地になってしまう可能性があります。「北風と太陽」ではありませんが、相手を正そうとはせず、じっくりと話を聞くことでスムーズに対話を始められます。途中で話をさえぎらず、まずは最後まで聞くことを心がけてみましょう。
質問を投げかける
カウンセラーは相談者に答えを提示するのではなく、質問を重ねながら相談者が「自分で解決の糸口を見つけた!」と感じられるような道筋を立てるといいます。相手の様子やシチュエーションに合わせて適切な問いを投げかけることで、相手が自分の考えを見直すきっかけを与えるのです。その手法にならって、質問をはさみながら会話を進めてみるのもお勧めです。
反論は冷静に伝える
こちらが感情的になると相手は「攻撃された」と受け取り、かえって話が進まなくなることがあります。相手の意見に反論をする場合は、感情的なことを挟まず「事実を冷静に伝える」ことが大切です。いったん議論が激化すると、お互いが引くに引けない状況になってしまうことも少なくありません。事前にデータや数字などの事実にもとづく素材が揃っていれば、相手も違う意見を受け入れやすいはずです。
適度な距離を保つ
どれだけ言葉を尽くしたところで分かり合えない相手はいます。そんな相手とお互いにつらい思いをしてまで関わる必要はありません。職場などでどうしても顔を合わせなくてはいけないような状況では、最低限の礼節を保ちながら、適度な距離感を意識してみましょう。
物理的に離れることが難しいときも、心の中で「あの人はこういう人だから仕方がない」と考えれば、少なくとも“心の距離”は守れます。人や物事に対してレッテルを貼るというと一方的な感じがして良くない意味で使われることが多いですが、それが必要になる場合もあるのです。
立場を変えて考えてもらう
「自分は正しい」という思いにとらわれている相手は、目の前の人がどんな思いをしているか?ということまで想像することができません。自分の意見に固執しているとき、人は視野が狭くなっています。そんなときは相手の言葉(行動)に対して、それを受けた自分(アイ)の視点で「私はこう思う」「私はこう感じた」とアイメッセージで伝えてみるのも効果的です。もしかすると相手が自分の言動を振り返るきっかけにもなるかもしれません。
余計な対立は避ける
話し合って解決できるレベルをすでに超えている場合、余計な対立を続けてもお互いにストレスがたまるだけです。そんな場合は適切なタイミングで「引く」という選択をした方がいいことも……。その後はできるだけ、その相手と揉めそうな話題は避ける方がいいかもしれません。
自分が正しいと思ってしまうのは病気の可能性も?
人の意見を受け入れることを難しく感じる状態が続く際は、何らかの精神的な問題が原因となっている可能性があります。発達障害のひとつの特性にも「自分のルールにこだわりすぎて、そこから外れることを過剰に拒む」という心情がみられます。
また、現実ではない妄想にとらわれる「妄想性障害」や、過大な自尊心や共感の欠如といった特徴を示す「自己愛性パーソナリティー障害」などの症状が影響していることも。人間関係でのトラブルが続いたり、それが生活に悪影響を及ぼしたりしている場合は、すみやかに医療機関や専門家に相談してください。
どこに相談したらよいか分からないという方は、以下の厚生労働省の相談窓口を利用してみましょう。
https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/(働く人のメンタルヘルス·ポータルサイト「こころの耳」)
まとめ
自分の考えや思いつきに固執してしまうのは、多かれ少なかれ誰にでもあること。ですが、そのような状態を改善しようとせずに放っておくと人間関係でのトラブルのもとになる可能性があります。もう少し他人の意見を尊重したり、相手の気持ちを想像したりできるようになれば、周囲から自然と「これ教えてください」と人が集まってきてくれるはずです。

\ この記事の監修者 /
ニューモラル 仕事と生き方ラボ
ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。
ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。
「自分が正しい」と思っている人の特徴や接し方について解説に関するおすすめ書籍はこちら
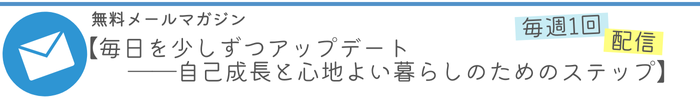


↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)
関連する投稿
-

2025年12月19日
-

人付き合いが苦手な人の6つの特徴とは?原因や克服方法についても解説
2025年08月22日
-

人と関わりたくないと感じるのはなぜ?原因や対処法について解説!
2025年07月30日
-

2025年07月15日
-

人のせいにしてしまう人の心理状態とは?特徴や対処法について解説
2025年06月19日
-

誰もわかってくれないと思ってしまうのはなぜ?要因ややわらげる方法を解説
2025年06月09日
人気ブログ
-

2024年08月14日
-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介
2024年05月29日
-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介
2024年02月21日
-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介
2024年02月09日
-

2024年01月24日
-

2024年01月13日
-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介
2023年12月20日
-

2023年12月11日
-

2023年10月31日
-
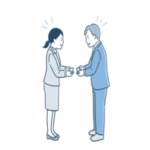
礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー
2023年10月13日

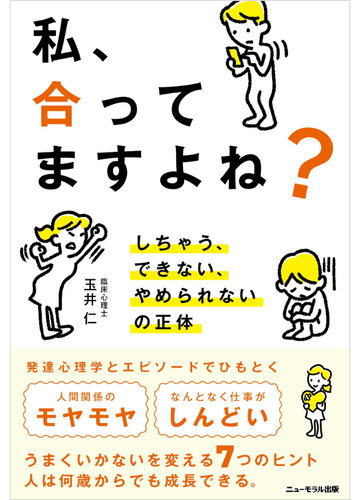
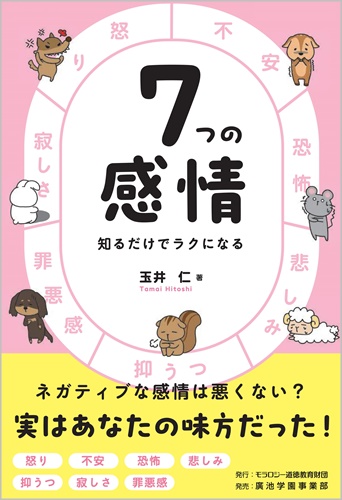
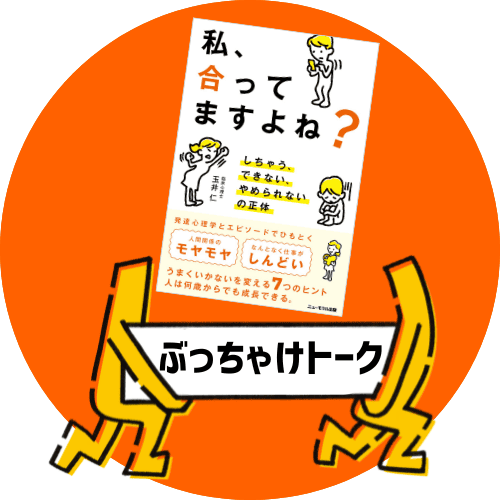
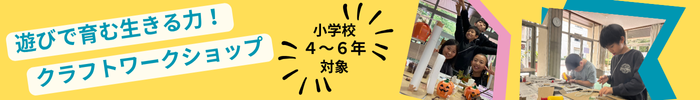









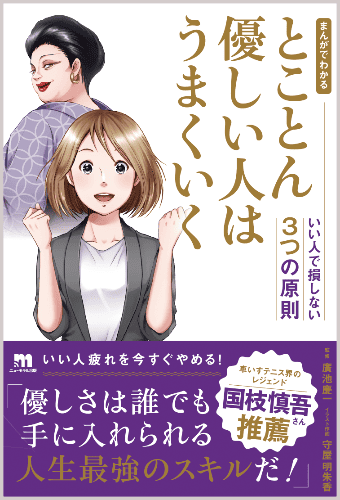
![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)
![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)